�����@�̑�������X�^�[�g |
 |
| ��P�́@2019�N7��1���{�s�̑����@�����i�{�s���ȍ~�ɑ����J�n�������̂ɓK�p�����j |
 |
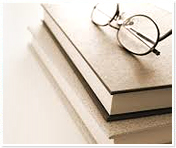
�P�D�o�q�̑�����
�@�o�q�̑��������A���o�q�̂Q���̂P�Ƃ��Ă����������폜���A�����Ƃ����i�X�O�O���j�B
�@����́A�o�q�̑��������Q���̂P�Ƃ���K����A�ō��ّ�@�약���Q�T�N�X���S���������ጛ�Ƃ������Ƃ������A�폜�������̂ł���B
�Q�D���������ƑR�v��
�@�����ɂ�錠���̏��p�́A�@�葊�������z���镔���ɂ��ẮA�o�L�A�o�^�A���̑��R�v��������Ȃ���A��O�҂ɑR�ł��Ȃ��ƋK�肳�ꂽ�i�W�X�X���̂Q�j�B
�@�]���A����ŋ��߂�ꂽ���̂��A�������������̂ł���B
�R�D�������̎w��
�@�����J�n���̈�Y�ɑ�����҂́A�⌾�ɑ������̎w�肪�����Ă��A�������ɉ����āA�������s�g�ł���B�������A���҂��������̎w��ɉ��������̏��p�����F�����Ƃ��͂��̌���ł͂Ȃ��Ƃ����i�X�O�Q���̂Q�j�B
�@������A�]���̔��ᗝ�_�𖾕����������̂ł���B
�S�D���^�A�②�ɂ��z��ҋ��Z���Y
�@�@�������Ԃ��Q�O�N�ȏ�̕v�w�́A����������ɁA���̋��Z�ɋ����Ă��錚���܂��͂��̕~�n���②�܂��͑��^�������Ƃ��́A��ɓ��ʎ�v�Ƃ��Ď����߂��K�v�͖����Ȃ����i�X�O�R���j�B
���ʎ�v�Ƃ��Ď������̂��K�v���Ȃ��Ȃ����͈͂ŁA�����������������Ƃ������ʂƂȂ�B
�����A��ł́A�������̑����ɔ�������̂��������Ƃ�z�����A�u���ʎ�v�̎��߂��Ə��̈ӎv�\���̐���v�Ƃ����A��Ȍ����ƂȂ��Ă���B
�@�A�{�s�O�ɂȂ��ꂽ���^�A�②�ɂ͓K�p����Ȃ����Ƃɒ��ӂ���K�v������B
�T�D��Y�����O�̍��Y����
�@�����J�n��ň�Y�̕����O�ɏ������ꂽ��Y�́A�����l�S���̓��ӂɂ��A��Y�̕������Ɉ�Y�Ƃ��đ��݂�����̂ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���Ƃ����i�X�O�U���̂Q�j�B
�@�]���́A��Y�̕����O�ɏ��������ƕ����̑ΏۂƂł����A�ʓr�A�����i�ד��ʼn������邵���Ȃ��������A����̉����ŁA��Y�Ƃ��đ��݂���Ƃł��邱�ƂƂȂ����B���̂��߁A����������҂ɑ��������āA���̕��A���̈�Y�ɑ��鐿����r���ł��邱�ƂƂȂ����B
�U�D�ꕔ����
�@��Y�̈ꕔ�������\�ł���Ɩ��L���ꂽ�i�X�O�V���j�B
�@�]������A�S�̂���藣���A�ꕔ�����̈�Y�������\�Ƃ���Ă������A���ꂪ���L���ꂽ�B
�V�D��Y�����O�̗a�������̍s�g
�@�e���������l�́A��Y�̒��̗a�������ɂ��āA�����J�n���̍��z�̂R���̂P�ɁA�e���̖@�葊�������悶�����z�ɂ��ẮA�P�ƂŌ������s�g�ł��邱�ƂƂȂ����i�X�O�X���̂Q�j�B�������A�ʓr�@���ȗ߂ŁA���Z�@�ւ��ƂɁA������P�T�O���~�Ƃ���Ă���B
�@�������J�n����Ɨa������������A�ً}�̑Ώ����ł��Ȃ��Ƃ����s�ւ��������B�܂��A�ō��ّ�@�약���Q�W�N�P�Q���P�X���������A�����O�̗a�����ɂ��āA�]���̕����������珀���L�����ɉ��߂��̂ŁA�a�����̒P�Ƃł̍s�g���ł��Ȃ��Ȃ����B�����ŁA�����̕s�s���������ׂ��A���͈͓̔��ŗa�����̒P�ƍs�g���\�Ƃ������̂ł���B
�W�D���M�؏��⌾�̍��Y�ژ^�i����Ɍ���A�P�X�N�P���P�R���ɐ�s�{�s�j
�@���M�؏��⌾�́A�S�����������A���t�����āA�L����������K�v�����������A�Y�t���鑊�����Y�ژ^�Ɍ����ẮA�����v����P�p���A�p�\�R���Ȃǂ̋@�B�ɂ��쐻�A���l�̑�M�Ȃǂ��L��������邱�ƂƂȂ����i�X�U�W���j�B
�@�����A�ژ^�쐻�ɓ������ẮA�ژ^�̊e�t�i���ʂ̎��́A���ʁj�ɏ������A��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���i�O���j�B
�X�D�◯���̔��{�I�����i�P�O�S�Q���`�P�O�S�X���j
�@�@�u�◯�����E�����v�łȂ��A�u�◯���N�Q�z�̐����v�ƂȂ�A�u���E�v�Ƃ����p�ꂪ�A����������B
�]���́u�◯�����E�����v�͕����I�`�����Ƃ���A�Ώۂ̑������Y�̌����Ԋ҂������Ƃ��ꂽ�B���̌��ʁA�����⎖�Ɨp���Y���Ԋ҂�������A������Ƃ̎��Ə��p�̂悤�ȏꍇ�A�o�c���̑��D�ɔ��W�����˂Ȃ��ƂȂ��Ă����B�����ŁA����̉����ŁA���K�I�������ɏ�������邱�ƂƂȂ����B���̌��ʁA���K�I�������ʼn�������悭�A�o�c���ɑ���e����r���ł���B
�@�A�◯�����Z�o���邽�߂̑��^�́A�]�O�́A�����J�n�O�̂P�N�ԂɌ��邪�A�����ґo�����◯�������҂ɑ��Q��^���邱�Ƃ�m���đ��^�����Ƃ��́A�P�N�O�̓����O�ɂ������̂��ΏۂƂ���Ă����B
����̉����ł́A�����l�ɑ��鑡�^�ɂ��ẮA�P�N���P�O�N�Ƃ��āA�啝�ɉ������B�Ȃ��A��O�҂ɑ��鑡�^�́A�]���ʂ�P�N����Ƃ��Ă���i�P�O�S�S���j�B
���̉����́A������Ƃ̎��Ə��p�ɂ����ẮA�Ӌ`���傫���B�����⎖�Ɨp���Y�̏��n�͂ł��邾��������p�҂̎q�̏��p�����邱�Ƃ����҂����B���n��A�P�O�N�ȏ㐶���ł���A�����Ƃ��Ĉ◯����N�Q���Ȃ����A�P�O�N�ȓ��ɖS���Ȃ�ƁA�◯���̂Ȃ��Ɏ�荞�܂�A���z�ُ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�������ł���B
�����ŁA�@�ƍ��킹�Ă܂Ƃ߂�ƁA���Ə��p�ł́A�◯����N�Q�����Ƃ��Ă��������̕Ԋ҂͂Ȃ��̂Ōo�c���ɉe����^���Ȃ����̂́A�P�O�N�ȓ��̎��Ə��p�ł́A�◯����N�Q����A���z�ُ��������āA�Z��Ԃ̌��������悤�Ƃ��邱�Ƃɂ��A�~���Ȏ��Ə��p�����҂��Ă���Ƃ����悤�B
���Ə��p�́A���n��P�O�N�ȏ㐶���ł���悤�A���߂ɂ��邱�Ƃ��������҂���Ă���ƌ����悤�B
�@�B�◯���N�Q�̉̂��߂ɂ́A�O�q�̒ʂ���K�I�����Ɍ����邪�A�����@�ł͂��̌v�Z���@�����m�ɂ��ꂽ�i�P�O�S�U���j�B
���e�́A�]���̔���i�ŎO�����W�D�P�P�D�Q�U�j���k���������̂ł���A�����I�ȕύX�͂Ȃ��Ǝv����̂ŁA�ȗ�����B
�@�C����̉����ł́A��^���ƈ◯���̊W�Ƃ����A�]������̓��ɂ́A�����Ă��Ȃ��B
�@�D���҂܂��͎҂̕��S�z�ɂ��ẮA�����O�̂P�O�R�R������P�O�R�V���܂ł̏�������������A���k������Ă���i�P�O�S�V���j�B
���Ȃ킿�A�②���������^�����O���^�̏��ŏ�������A�������ҁA�҂̊Ԃł́A���ꂼ�ꊄ���I�ɕ��S���邱�ƂɂȂ�B
�@�@�◯���N�Q�z�ɑ��鐿�����́A�◯�������҂��A���Q�̊J�n�y�ш◯����N�Q���鑡�^�����邱�Ƃ�m���Ă���P�N�ԍs�g���Ȃ��Ƃ��͎����ɂ����ł���B�����J�n����P�O�N���o�߂����Ƃ������l�Ƃ���i�P�O�S�W���j�B
�`�����̍s�g���������̎����ɂ�����������ŁA�����I�ȕύX�͂Ȃ��B
�@�A�◯���̕����ɂ��ẮA�����I�ȕύX�͂Ȃ��B
�P�O�D���ʂ̊�^�̐V��
�@�@�푊���l�ɑ��Ė����ŗ×{��삻�̑��̘J���̒����āA�푊���l�̍��Y�̈ێ��܂��͑����ɂ��ē��ʂ̊�^�������푊���l�̐e���i�j�́A�����̊J�n��A�����l�ɑ��āA���ʊ�^���𐿋��ł���i�P�O�T�O���P���j�B
�e���Ɋւ��ẮA�����l��������鑼�A�����������������́A���i�ҁE�r���҂��������B
�e���́A���@�V�Q�T���̒�߂���̂Ȃ̂ŁA��̓I�ɂ́A�푊���l�̔z��ҁA�푊���l�̌Z��o���y�т��̔z��ҁA�푊���l�̌Z��o���̎q�y�т��̔z��ҁA�푊���l�̔z��҂̘A��q�Ȃǂł��낤�B�}�{�`���W�ɂ�����̂Ɍ��肳��Ă��Ȃ��B
�����́A�v���ł͂Ȃ��B
�×{��삾���łȂ��A�_�Ƃ⎩�c�Ƃ̎�`���Ƃ����J�����܂ނ��A�����Ŗ�����Ȃ�Ȃ��B
�@�A�����҂ɋ��c������Ȃ��Ƃ��́A�ƒ�ٔ����ɋ��c�ɂ���鏈���𐿋��ł���B�������A�����̊J�n�y�ё����l��m���Ă���U�������o�߂����Ƃ��A�܂��́A�����̊J�n��m�����Ƃ�����P�N���o�߂����Ƃ��́A���̌���ł͂Ȃ��i�����j�B
�@�B��^���̊z�͑����J�n���̍��Y�̊z����②�̉��z���T�������c�z�����Ȃ��B�܂��A�����l�̕��S�́A�@�葊�����̊����ɂ��i���S���A�T���j�B
| ��Q�́@�Q�O�Q�O�N�S���P���{�s�̑����@���� |
 |

�P�D�z��ҋ��Z��
�@�@�푊���l�̔z��҂́A�푊���l�̍��Y�ł��錚���ɑ����J�n���ɋ��Z���Ă����ꍇ�́A
�@�D��Y�̕����ɂ��z��ҋ��Z�����擾������̂Ƃ��ꂽ�Ƃ�
�A�D�z��ҋ��Z�����②�̖ړI�Ƃ��ꂽ�Ƃ�
�ɂ́A���̌����̑S���ɂ��āA�����Ŏg�p���v���錠���i�u�z��ҋ��Z���v���擾����B
�������A�����J�n���ɁA�������z��҈ȊO�̂��̂Ƌ��L����Ă���Ƃ��͂��̌���łȂ��i�P�O�Q�W���P���j�B
�@�A���Z�����擾�����z��҂����Z�������擾����ƍ����ŋ��Z���͏��ł���͂������A���̌�A���̎҂����L��������L����Ƃ��́A���Z���͏��ł��Ȃ��Ƃ݂Ȃ����i����Q���j�B
�@�B�������Ԃ��Q�O�N�ȏ�̕v�w�̈�������S�����ꍇ�A�����z��҂ɔz��ҋ��Z�����②�����Ƃ��́A�����܂��͂��̕~�n���②�����Ƃ��̋K��ł���X�O�S���S�������p���A�����߂��Ə��̈ӎv�\�������������̂Ɛ��肳���i���R���j�B
�������^�_��͈②�̋K������p����i���@�T�T�S�j�̂ŁA�������A�����߂��Ə��̈ӎv�\�������������̂Ɛ��肳���B
�@�C��Y�̕������������ƒ�ٔ����́A���Ɍf����ꍇ�Ɍ���A�z��҂����Z�����擾����|���߂邱�Ƃ��ł���B
�@�D���������l�ԂɁA�z��҂��z��ҋ��Z�����擾���邱�Ƃɂ��āA���ӂ��������Ă���ꍇ�B
�A�D�z��҂��ƒ�ٔ����ɔz��ҋ��Z���̎擾����]����|��\���o���ꍇ�ɂ����āA���Z�����̏��L�҂̎�s���v���l�����Ă��A�Ȃ��z��҂̐������ێ����邽�߂ɓ��ɕK�v������ƔF�߂��ꍇ
�@�D�z��ҋ��Z���̑������Ԃ́A�z��҂̏I�g�Ƃ���B�������A��Y�������c�A�⌾�̒�߁A�܂��́A��Y�����̐R���̂����ĕʒi�̒�߂������Ƃ��͂���ɏ]���i�P�O�R�O���j�B
�@�E���Z�����̏��L�҂́A�z��ҋ��Z���ݒ�̓o�L��ݒ肷��`�����i�P�O�R�P���j�B
�@�F�z��ҋ��Z���́A���n���邱�Ƃ��ł��Ȃ��i�P�O�R�Q���Q���j
�@�G�z��҂́A�]�O�̗p�@�ɏ]���āA�P�ǂȊǗ��҂̒��Ӌ`���������Ďg�p�E���v������`�����B�������A���Z�̗p�ɋ����Ă��Ȃ����������ɂ��āA���Z�̗p�ɋ����邱�Ƃ����܂����Ȃ��i�����P���j�B
�z��҂́A���L�҂̏��������A���z�������͑��z�����A�܂��́A��O�҂Ɏg�p�E���v�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��i����R���j�B
�z��҂������Ɉᔽ���A�����̊��Ԃ��߂����������ɏ]��Ȃ��Ƃ��́A���L�҂͔z��ҋ��Z�������ł����邱�Ƃ��ł���i����S���j�B
�@�H�z��҂́A�g�p�E���v�ɕK�v�ȏC�������邱�Ƃ��ł���i�P�O�R�R���P���j�B�z��҂��K�v�ȏC���𑊓��Ȋ��ԓ��ɂ��Ȃ��Ƃ��́A���L�҂͂��̏C�������邱�Ƃ��ł���i����Q���j�B
�@�I�z��҂́A���Z�����̒ʗp�̕K�v��i�Œ莑�Y�ł�ʏ�̏C����Ȃǁj�S����B���ʂ̕K�v��i�����Q�ɂ��C����Ȃǁj��L�v��i���t�H�[����p�Ȃǁj�͏��L�҂̕��S�ł��邪�A�����z��҂��x�������ꍇ�ɂ͏��L�҂ɑ��ď��҂ł���i����Q���ɂ�閯�@�T�W�Q���Q���̏��p�j�B
�Q�D�z��ҒZ�����Z��
�@�@�푊���l�̍��Y�ɑ����Ă��������ɁA�����̊J�n���ɖ����ŋ��Z���Ă����z��҂ɂ́A�����̊J�n�Ɠ����ɔz��ҒZ�����Z������������B����́A��Y�����ɂ�苏�Z�����̋A�����m�肵�����A�܂��́A�����J�n�̎�����U�������o�߂�����̂����ꂩ�x�����܂ő�������i�P�O�R�V���j�B
�@�A�z��ҒZ�����Z���͖��������A�������Ƃ��Ĉ���Ȃ��B
�@�B�z��҂́A�]���̗p�@�ɏ]���`���ƑP�ǒ��Ӌ`�����A���v���͖����B�܂��A���n�͂ł��Ȃ�
| ��R�́@�Q�O�Q�O�N�V���P�O���{�s�̈⌾���̖@���Ǖۊ� |
 |
�P�D�⌾���̕ۊ�
�@�@���@�̉����Ƃ͕ʗ��ĂŁA�@���ǂɂ��A�⌾���̕ۊǓ��Ɋւ���@�������肳�ꂽ�B
����ɂ��A���M�؏��⌾�́A�{�l�m�F�ƈ⌾���̕����̐R����������ŁA����̎葱���ɂ��A�@���ǂɕۊǂł��邱�ƂƂȂ����B
�@�A�@���ǂɂ��ۊǂ��ꂽ�⌾���́A���F�葱���͕s�v�ƂȂ�B

�����g���u���̌��� |
 |
| ��P�́@�e�̉��͑��������̎�ɂȂ�₷�� |
 |
 �@�ٌ�m�������̑��k�ɗ��鑊���g���u���̂��������͐e�̉��ɋN������Ƃ����Ă����قǁA�e�̉��͑�����������N���₷���B
�@�e��������������̉��͕s���ł��邪�A�Z��o���̂������ꂪ���S���邩�����ł���B�����������҂Ƃ����łȂ��҂Ƃ̊ԂŁA�ǂ����Ă��s��������������B
�@�e���������҂͓��ʂ̋�J�Əo����������邪�A���̋�J�𑼂̌Z�킪�F�����Ă��Ȃ����Ƃ������B���̌��ʁA�e�������ƁA���������҂͂��̕��S����Y�����̒��ōl�����邱�Ƃ����߂邪�A���̌Z��͂�������悤�Ƃ���̂ŕ����ƂȂ�̂��B
�@�t�̎��Ԃ�����B�e�Ɠ������Ă���ƁA�e���g�߂ɂ��邱�Ƃ���e���玑���������邱�Ƃ������A�܂��A�����ɔ����Ď����ɗL���Ȉ⌾�����������悤�Ƃ��邱�Ƃ������B�e�͖ʓ|�����ė~������S����A�������Ă����q�̂��߂ɐϋɓI�ɗL���Ȉ⌾�����������������B�����Ȃ�ƁA�t�Ɉ�l�����L���ȗ���ɂȂ�B����ɁA�L���Ȉ⌾�����������邽�߂ɁA�ϋɓI�ɐe��������낤�Ƃ��āA�Z��Ɲ��߂邱�Ƃ�����B
�@�܂��A�e�������������ɕK�������e�Ə�肭�����Ƃ͌��炸�A�e������������̂ɂ낭�ȉ������Ȃ������Ɣ���邱�Ƃ������A�����Ȃ�Ƒ����ɗ��܂������Q�W�͕��G�ƂȂ�A�[���ȑ��������̌����ƂȂ�̂��B
| ���� |
| ��삷��ɓ������ẮA���ꂪ�������A�N���ǂ���p���S���邩�A�@�葊���l�Ԃł悭�b�������Ă������Ƃ��]�܂����B�����J�n��̕����������O�ɌZ��ԂŘb�������Ă����āA���̌��ʂ�e�ɔ[�����Ă��炢�A�����D�荞�⌾���������Ă����Ă��炤�ƌ��ʓI�ł���B |
| ��Q�́@���Y�������Ă����Ȃ��Ă����߂� |
 |
���Y�̏��Ȃ��ꍇ
�@���Y���A�e�̏Z��ł����y�n�E�������傽����̂Ƃ����ꍇ�A������Č����ŕ�����悢���A�����ɒ��j���Z��ł��Ĕ��p�ɉ����Ȃ��Ƃ������Ƃ������B���̏ꍇ�A���j���㏞���Ƃ��đ��̌Z��̎���������邱�Ƃ��o����悢���A���ꂪ�o���Ȃ��ƕ����ɂȂ�B
| ���� |
| ���̎��Ԃ͗\�z�ł���̂ŁA���j�͑㏞���̎�����\�ߗp�ӂ��邩�A���̎��_�ő��ɓ]������p�ӂ����Ă����K�v������B |
���Y�̑����ꍇ
�@���Y�������Ă��A���߂邱�Ƃ͑����B�s���Y�ł����͂�����̂́A�F�����l���ł��邱�Ƃ������A��荇���ɂȂ�B
�@�e�����Y�Ǘ����Ă���悢���A���O����Ǘ��͒��j�������čs���Ă��邱�Ƃ������B���̏ꍇ�A���j�̓s���Ŕ��p���Ă��܂�����A�݂�����A�r���������肷��B���̊ԂɁA����������s���s���ƂȂ��Ă�����A�Ǘ����@�ɑ��̌Z�킪�s���������Ă��邱�Ƃ������B�ƂȂ�ƁA�ォ����߂邱�Ƃ͕K��ł���B���Y�����������ɁA�[���ȑ��������ɂȂ邱�Ƃ������B
| ���� |
���Y���������́A�⌾�����c���đ��������O�ɖh�~����Ƃ����̂��e�̋`���ƌ����ׂ��ł���B���e���K�i�ł���A�����𖢑R�ɖh�~�ł���B
���������ۂ́A�⌾�������邱�Ƃ͑����͂Ȃ��B�⌾���̕K�v���͂����ƌ[�ւ����ׂ��ł��낤�B |
| ��R�́@��^���E���ʎ�v�͝��߂₷�� |
 |

�@��^���́A�����l�̈�l����Y�̌`���E�ێ��Ɋ�^�����ꍇ�ł���A��^���͊�^�҂��ʘg�ő������邱�ƂƂȂ�B
�@���ʎ�v�́A�@�葊���l�̈�l���e������ʂ̑��^����ꍇ�ł���A���̕��͈�Y���獷��������邱�ƂƂȂ�B
�@���͂����̗L���̔��f�Ƃ��̊z�̎Z��ł���B��^�����Ǝ咣���Ă����̑����l�������F�߂Ȃ�������A���ʎ�v������Ǝ咣���Ă����Ƃ����҂������F�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ͑����B���͍���Ȃ��Ƃ������A�[���ȕ����ƂȂ�B
| ���� |
| ��^���A���ʎ�v�̎咣�͎��O�ɗ\�z�ł���͂��ł���B�咣�������҂��A�h�䂵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��҂��A�\�ߏ؋��������W�߂Ă����K�v������B |
| ��S�́@���e���Ⴄ�E���Ⴂ�E�o�q�Ƃ����͕̂����̎� |
 |
�����̏ꍇ�́A���a�ɉ����ł�����b�L�[�ƌ����ׂ��ł���B
| ���� |
��D�͈⌾���ł���B�⌾���̍쐬�����Ă������Ƃ͐e�̋`���ł���B
�⌾���̖������́A�b������������Ƃ܂��܂��������Ƃ������Ƃ������̂ŁA���߂ɐ��Ƃɒ����𗊂����悢�ł��낤�B |

���������́A�u�����������Z���^�[�v�ƒ�g���A�אڕ���̐��ƂƂƂ��ɁA�����I�ȑ�Ɖ������}���悤�ɂȂ�܂����B
�u�����������Z���^�[�v�̃����o�[�Ƃ��āA�@���ʂ���A�����g���u���̉����Ƃ��̗\�h��S�����܂��B��Y������A�⌾���̍쐬�͓����������Ώ����܂��B
�u�����������Z���^�[�v�́A���F��v�m�E�ŗ��m�A�ٌ�m�A�i�@���m�A�s���Y�Ӓ�m�A�y�n�Ɖ������m�A�ꋉ���z�m�ɂ����ƃO���[�v�ł��B
�����Ɋւ���A������P�[�X�ɂ��āA�@���I�����ʓI�ɑΏ��ł��܂��B

������͖��S�ł��傤���H
�����Ɋւ���@�����k�́A���ٌ̕�m�ɂ��C�����������I
������́A�ł��邾�������i�K����s���قnj��ʂ������A����Ԃ������قǗL���ȑ��ĈՂ��̂ł��B��̓I�ɂ́A�N�������l�ɂȂ邩�A���̖@�葊�����͂ǂ̂��炢�����m�F���������ň⌾�����쐬���邱�ƁA�܂��A�����ł��ǂ̂��炢�ɂȂ邩���T�Z���A�ǂ̂悤�ɔ[�ł��邩���l���Ȃ���A�ߐő���u���邱�Ƃ��K�v�ł��B�P�������݂̂Ȃ炸�A�Q�������₻�̌�̑����l�̐������𑍍��I�ɍl�����āA�����I����ɗ����đ���u����K�v������܂��B�����̎��܂��A�����Ɋւ���@�����k�́A���ٌ̕�m�ɂ����k���邱�Ƃ��������ߒv���܂��B
 ����������l���̕��ցI
����������l���̕��ցI ���������I�ł�������������̂�������Ȃ��B
���������I�ł�������������̂�������Ȃ��B
����ȂƂ��́A�ȉ���6 �X�e�b�v�����Ɋm�F���Ă݂Ă��������B
�������������̎��́A�����Ɋւ���@�����k�́A���ٌ�m�̋��q�E���R�@���������ɂ��A���������������`�������Ă��������܂��B
- �����l�́H
�ʏ�́A�����l�͂����킩��͂��ł����A�����ɂ͖S���Ȃ������ɉB���q�����ĔF�m���Ă����Ƃ��A���������ɗ{�q�ɏo���ꂽ�Z��o���������Ƃ������Ƃ�����܂��B �O�̂��ߔ푊���l�̌ːГ��{�����āA�����l���N�Ȃ̂����m�肳���܂��傤�B
- �⌾���͂���܂����H
�⌾���ɂ́u���M�؏��⌾�v�u�����؏��⌾�v�u�閧�؏��⌾�v������܂��B�⌾���̗L�����m�F���A�⌾��������ꍇ�ɂ͂��̈⌾���ɏ]���č��Y�̕��������܂��傤�B�⌾�������āA��Y�������Ă��A�����ł��B
- ���Y�Ǝ؋��̓��e���m�F���܂��傤
�S���Ȃ������̍��Y�Ǝ؋����m�F���܂��傤�B�����ł̐\�������o�����ꍇ�ɂ́A�Ŗ��������̑����ł̌v�Z�����������ǂ������ɗ���\���������ł��B���̂Ƃ��ɉB�����Y�Ȃǂ��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
- ��Y�������c�����܂��傤
(1)��{�́A���@�Œ�߂�ꂽ�@�葊�����ł��B��Y�����̕��@�͌��������A�㏞�����A�㕨�����A�������� �A���L����������܂��B(2)�����l�̊Ԃň�Y�̕������m�肵����A��Y�������c�����쐬���܂��傤�B
- ���Y�̕]�������܂��傤
�K�v������A����(�s���Y�Ȃ�s���Y�Ӓ�m�Ȃ�)�Ɉ˗����܂��傤�B�����I�ȕ������ł��邵�A�����ł̐ߐłł���ꍇ������܂��B
- �����ł̐\�������܂��傤
�S���Ȃ��Ă���P�O�����ȓ��ɐ\�����̒�o�Ɣ[�t�����Ȃ���Ȃ�܂���B����܂łɈ�Y�������ł��Ȃ���A���̐\�����A�����ł�[�t����K�v������܂��B
 �����Ɋւ���@�����k�́A���ٌ̕�m�ɂ��C�����������I
�����Ɋւ���@�����k�́A���ٌ̕�m�ɂ��C�����������I
�����͐l���̒��ʼn��x���o�����邱�Ƃł͂���܂���̂ŁA�o���L�x�Ȑ��ٌ�m�ɂ����k�������Ƃ��������ߒv���܂��B���q�E���R�@���������ł́A�����Ɋւ���@�����k����A�����̎葱�����@�ȂǁA���ٌ̕�m���g�[�^���I�ȃT�|�[�g��v���܂��B���q�E���R�@���������ւ̖@�����k�Ɋւ��܂��ẮA �@�����k�̕��@�����Q�Ƃ��������B

�����œ��̐ߐő�͏d�v�I |
�@�����ł̍T�������͕����Q�V�N�P���P����茵�����Ȃ�B���̂��߁A�����ł�[�ł���K�v�̂���҂͋}�����A�����ł̐ߐő�͏d�v�Ȃ��̂ƂȂ낤�B
�@�����ł̐ߐłɂ͐F�X�ȕ��@���l������B���ɁA���̕��@���Љ��B
�@���������́A�����ł̐ߐō���܂߂āA�����̑��S�ʂ̎x�������邱�Ƃ�ڎw���Ă���B |
 |
| ��P�́@���O�����ɂ��l�̑����œ��̐ߐ� |
 |
�����łɂ��ẮA�傫�ȉ���������̂ŁA���ӂ�v����B
�E�����ł̉����̃|�C���g
�P�D�l���Ƃ�@�l���肷�邱�Ƃɂ��ߐ�
 �@�����Ŗ@�͒��ߗݐi�ŗ��Ȃ̂ŁA�@�l�ɂ��āA���������łȂ��Ƒ��֖�����V�⋋�����o�����Ƃɂ���āA�����̕��U����}��䂱�Ƃɂ��A�ߐŌ��ʂ�����B
�@�����ő�Ƃ��ẮA��Y�Ƃ����ɑ����l�ŗL�̎����Ƃ��邱�Ƃɂ��A��Y�����炷���Ƃ��ł���B
�Q�D�s���Y��@�l�ɏ��L�����邱�Ƃɂ��ߐ�
- �E���L�s���Y�������o���ɂ��s���Y�ۗL��Ђ�ݗ�����B���ɂ���@�l�ɔ��p���邱�Ƃł��悢�B
�E������V�A���^���Ƒ��ɕ��U����B�ݐi�ېł�������邱�Ƃ��ł��邵�A���^�����T�����g����̂ŁA�����ł̐ߐł��ł���B�������A���^�����T���̑����s�Z���̋K��ɒ��ӁB
�E���ݏZ��̎擾�Ɋւ������ł̊ҕt���g����B
�E�T�����[�}���̑�Ƃ́A�T�����[�ɕs���Y������������Ă��܂��̂ŁA�@�l���ɂ��ߐŌ��ʂ͑傫���B�@�l�̖������Ȃɂ��邱�Ƃ������B
�E�s���Y�������P�T�O�O���~���郌�x���̏ꍇ�A�@�l���͌��ʓI�ł���B
-
�E�e����q�Ɋ��������Ԃ������ď��������n����B
�E�ݗ�������Ђ̊����𐄒葊���l�ɕ������^���A�ƒ������𐄒葊���l�ł킯��ƐߐŌ��ʂ͑傫���B
�E�e�����������L���Ă���Ԃ́A�����̕]���������邱�Ƃ��l����ׂ��ł���B
���������邩�A�T���ΏۂƂȂ鑹���������V�𑝂₷�B���邢�́A�ސE�����x������B�i�ސE���͐ŗ����L���ŁA�T�����傫���j
-
�E�����ŋ��L�ƂȂ����Ƃ��A�܂Ƃ߂Ė@�l�ɏ��n����Ƃ悢�B
�E�����Ŋz�̎擾����Z�̓K�p���邱�Ƃ��ł���s���Y���������ɔ��p�ł��Ȃ������Ƃ����A�@�l�ɔ��p���邱�Ƃɂ��A����̓K�p���邱�Ƃ��ł���B
- �@�l�����邱�Ƃɂ�錇�_
�@ �@�l�ւ̏��n�ɂ����锄�p�v�����ł���B�����o�����A���������ƂȂ�B
�y�n�������̔����ȉ��ɂ���ƁA���^�ł���������̂Œ��ӁB
�擾�����Ȃ��ƁA���p����̂P�X���Ƃ����B
�@
����
�@�E�����̂ݏ��n���A�y�n�͎��i�����͕뉿�łn�j�j
�@�E�y�n�̒��ɂ����āA������������ɁA�Ŗ������Ɂu�����Ԋ҂̓͂��o�v���o���Ă����B
�@�E�����Ŋz�̎擾����Z�̓K�p���邱�Ƃ��ł���s���Y���������ɔ��p����B
�@�E���̕s���Y�̏��n���������������N�x�ɁA�@�l�֔��p����B
�A�o�L��p�A�s���Y�擾�łȂǂ̏����o�������B
�B�l����̕s���Y���[���̕ԍς��I����Ă��Ȃ��ƁA�@�l�̎����ɐ�ւ���K�v������B
�R�D�T�u���[�X�@�l�ɂ��ߐ�
- ���Ȃ̕s���Y�ڑ�O�҂ɒ��݂������ɁA�s���Y��@�l�ɒ��݂��A��O�҂ɓ]�݂���B���̃T�u���[�X�ł���B
�@�l�́A�����ɑ��P�O�`�Q�O���̎萔����B����ɂ��A�������Y�����k���邱�Ƃ��ł���B
�@�l�ɂ����ĉƑ�������ɂ��邱�Ƃɂ�菊���U�ł���̂ŁA�����ł̐ߐłɂȂ�B
�����ɓ�d�T�����Ȃ��̂ŁA���L��������A�ߐŌ��ʂ͗��B
�s���Y�ɂ��āA�l�̃��[���̕ԍς��I����Ă��Ȃ������g����B
- �Ŗ����ɔ۔F����Ȃ����߂ɒ��ݎ،_��m�ɂ��A���ݎ،_��̐ؑւ���Ǘ��ϑ��_��A�����̓��������m�ɂ���B
�S�D�s���Y�Ǘ��@�l�ɂ��ߐ�
�E�@�l�ɕs���Y���Ǘ���������@�ł���B
�E�T�u���[�X�̏ꍇ�Ɠ����悤�ɁA�����łƏ����ł̐ߐŌ��ʂ�����B
�E�Ǘ���o�����邾���Ȃ̂ŁA���L�A���݂ɔ�ׁA�ߐŌ��ʂ͔����B
�T�D�e�̎����Œ��ݏZ��
- �E�Ⴆ�A�P���~�̒��ݏZ���e�̔�p�Ō��z����ƁA���ݏZ��͌��z��̂S�Q�����x�̕]���Ȃ̂ŁA���Y���l���T�W���Ɉ��k�ł���B
�E�e������������ƁA�ƒ��������������Y�ƂȂ�̂ŁA�P�O�`�Q�O�N�ŐߐŌ��ʂ͏��ł���B��Y����������̂ŁA�t�ɑ����ł������邱�Ƃ�����B
- �E���̕��@�ƁA�Q�D�s���Y��@�l�ɏ��L�����邱�Ƃɂ��ߐ��́A�s���Y��@�l�ɏ��L��������@���r���āA�ǂ��炪�L�����������ׂ��ł���B
�E�e�̏o�����Ŗ@�l��ݗ����A���������������^������@���x�^�[�Ȃ��Ƃ������B
�����𐄒葊���l�ɕ������^���A�ƒ������𐄒葊���l�ł킯�Ă��A�傫�Ȑߐł�����͂��ł���B
�����ጟ����
 �n�ɃA�p�[�g�����z���鎖��B
�n�ɃA�p�[�g�����z���鎖��B
�y�n6000���~�i�H�����]���j�A�y�n���L�҂��A�p�[�g��4000���~�Ō��z������
�ؒn������6���A�؉ƌ�����3��
�����b�g1�@�y�n�̕]����
�A�p�[�g�̕~�n�́A�݉ƌ��t�n�i�����₽�Ă����j�ƂȂ�A2�����x�̕]�����B
���̎���̏ꍇ�ł�6���̎ؒn���~3���̎؉ƌ���18���ƂȂ�B
�A�p�[�g�̕~�n�̕]���i�����ŕ]���j�@
6000���~�~�i1�|60���~30���j��4920���~
6000���~�|4920���~��1080���~�̕]�����ƂȂ�B
�����b�g2�@�����̕]����
���z��@4000���~�i�a���̌������͍��̑����j�B�Œ莑�Y�ŕ]���́A���z��̊T��7�����x�B�؉ƌ������R���B
�����̕]���i�����ŕ]���j
4000���~�~70���i�Œ莑�Y�ŕ]���ɏC���j�~�i1�|30���j��1960���~
4000���~�|1960���~��2040���~�̕]�����ƂȂ�B
�����b�g3�@���K�͑�n���̕]�����̂��߂̌��n�ƂȂ��B
�n�̂܂܂ł́A�푊���l�̎��Ɩ��͋��Z�p�̓y�n�ł͂Ȃ��̂ŏ��K�͑�n����I������Ƃ��̌��n�ɂ˂�Ȃ��B�������A�A�p�[�g�̕~�n�́A���Ɨp�̓y�n�Ƃ���200���Ă܂�50�����z������\��������i�������A���K�͑�n���́A��{�I�ɂ͈�Y�̒��ōł��L���ȓy�n����K�p����̂ŁA���ɗL���ȓy�n������A�L���ȕ�����K�p����j�B
�f�����b�g
�����̕ԍς�A�Ǘ���p�̕��S�A���A���p�̍��������B
�U�D�z��҂ւ̑��^ �������Ԃ�20�N�ȏ�̕v�w�̊ԂŁA���Z�p�s���Y���͋��Z�p�s���Y���擾���邽�߂̋��K�̑��^���s��ꂽ�ꍇ�A��b�T��110���~�̂ق��ɍō�2,000���~�܂ōT��(�z��ҍT��)�ł���Ƃ������Ⴊ����B
- ������邽�߂̓K�p�v��
�@ �v�w�̍������Ԃ�20�N���߂�����ɑ��^���s��ꂽ����
�A �z��҂��瑡�^���ꂽ���Y���A�������Z�ނ��߂̍����̋��Z�p�s���Y�ł��邱�Ɩ��͋��Z�p�s���Y���擾���邽�߂̋��K�ł��邱��
�B ���^�����N�̗��N3��15���܂łɁA���^�ɂ��擾���������̋��Z�p�s���Y���͑��^�������K�Ŏ擾���������̋��Z�p�s���Y�ɁA���^�����҂������ɏZ��ł���A���̌�����������Z�ތ����݂ł��邱��
(��)�@�z��ҍT���͓����z��҂���̑��^�ɂ��Ă͈ꐶ�Ɉ�x�����K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
- �z��҂ւ̑��^�͑��^�ł̐ߐłƂȂ邪�A�������Y�̈��k�ɂȂ�̂ŁA�����ł̐ߐłƂȂ�B
�V�D���^��b�T���P�P�O���~�̗��p
- ���^�T���ɂ���
�E���^�ɂ͊�b�T���P�P�O���~������̂ŁA�P�P�O���~�ȉ��̑��^������Ƒ��^�ł�������Ȃ����A�������Y�̈��k�ɂȂ�B
�E�������Y������قǑ����Ȃ����i�P���~�ʈȉ��j�̎��́A�����ł̐ߐłƂ��āA���̕��@�����ʓI�ł���B
�E�`���A�����N�ԂɁA�a�ɂP�O�O���~�A�b�ɂT�O���~�A�c�ɂW�O���~���^�������A�a�C�b�C�c�͂��̂P�N�ɑ����瑡�^���Ă��Ȃ����́A�N�����^�ł͉ېł���Ȃ��B�������A�a��������A���̔N�ɂT�O���~�̑��^���Ă������́A�a�͑��^�ł��ېł����B
�E�����J�n3�N�ȓ��̑��^�́A�������Y�ɉ��Z����邱�Ƃɒ��ӁB
�E���^�҂���10�N�Ԃɂ킽���Ė��N100���~�����^���邱�Ƃ���Ă���ꍇ�́A1�N���Ƃɑ��^����ƍl����̂ł͂Ȃ��A�������N�ɒ�����Ɋւ��錠���i10�N�Ԃɂ킽�薈�N100���~���̋��t���錠���j�̑��^�������̂Ƃ��đ��^�ł�������̂ŁA���ӂ�v����B
- ���^�̔۔F�ɒ���
�E�����Ő\�����ɁA���^���۔F����Ȃ��悤�A���^�_��m�Ƃ���ƂƂ��ɁA�����̓����m�ɂ��邽�߁A��s�������g���B�@
�E�P�Q�O���~���^���A�҂��m��\�������đ��^�ł��P���~�x�����̂��Ӗ�������B�\���͖ʓ|�����A����ɂ��A���^���۔F����邱�Ƃ͂܂��Ȃ��Ȃ�͂�������ł���B
�W�D�ی����g���ߐ� �E�e���q�̕ی����S���āA�q�������ی��_������Đe���ی��҂Ƃ���B�ی����ɂ��āA�N�P�P�O���~�̑��^�ł̔�ېŘg�𗘗p����ƁA���^�ł͂����炸�A�������Y����������B�ߐŌ��ʂ͑傫���B
�E�ی����́A�q�̔[�Ŏ����ƂȂ邵�A�q�ւ̉����ƂȂ�B
�X�D���玑���̑��^
- �E���玑���̈ꊇ���^�ɌW�鑡�^�Ŕ�ېő[�u�́A���^�ł̐ߐłƂȂ�ƂƂ��ɁA�������Y�̈��k�ɂ��A�����ł̐ߐłƂȂ�B
�E�c����i���^�ҁj�́A�q�E���i�ҁj���`�̋��Z�@�ւ̌������ɁA���玑�����ꊇ���ċ��o����B���̎����ɂ��āA�q�E�����Ƃ�1,500���~�܂ł��ېłƂ���B
�w�Z���ȊO�̎҂Ɏx��������̂ɂ��Ă�500���~�����x�Ƃ���B
�E���玑���̎g�r�́A���Z�@�ւ��̎��������`�F�b�N���A���ނ�ۊǂ���B
�E������30�ɒB������Ɍ������͏I������B���̎��̎c�z�ɂ��ẮA���^�ł�������B
�E����́A����25�N�S���P�����畽��27�N12��31���܂ł̂R�N�Ԃ̑[�u�ł���B
- �����ł̋��玑���Ƃ͊w�Z���ɑ��Ē��ڎx�����鎟�̂悤�ȋ��K
�A ���w���A���Ɨ��A�������A�ۈ痿�A�{�ݐݔ���͓��w�i���j�����̌��藿�Ȃ�
�C �w�p�i��A�C�w���s��A�w�Z���H��ȂNJw�Z���ɂ����鋳��ɔ����ĕK�v�Ȕ�p�Ȃ�
- �u�w�Z���v�Ƃ�
�E�w�Z����@��̗c�t���A���E���w�Z�A�����w�Z�A��������w�Z�A���ʎx���w�Z�A�������w�Z�A��w�A��w�@�A��C�w�Z�A�e��w�Z
�E�O���̋���{��
�k�O���ɂ�����́l���̍��̊w�Z���琧�x�Ɉʒu�Â����Ă���w�Z�A���{�l�w�Z�A�����݊O����{��
�k�����ɂ�����́l�C���^�[�i�V���i���X�N�[���i���ۓI�ȔF�؋@�ւɔF������́j�A�O���l�w�Z�i�����Ȋw��b�����Z�����Ƃ��Ďw�肵�����́j�A�O����w�̓��{�Z�A���ۘA����w
�E�F�肱�ǂ������͕ۈ珊�Ȃ�
- �w�Z���ȊO�ɑ��Ē��ڎx�����鎟�̂悤�ȋ��K�ŎЉ�ʔO�㑊���ƔF�߂�����̂��ΏۂƂȂ�
�@ ���͎w�����s���ҁi�w�K�m�␅�j�����Ȃǁj�ɒ��ڎx���������
�E ����i�w�K�m�A�����Ȃǁj�Ɋւ���̒̑Ή���{�݂̎g�p���Ȃ�
�E �X�|�[�c�i���j�A�싅�Ȃǁj���͕����|�p�Ɋւ��銈���i�s�A�m�A�G��Ȃǁj���̑����{�̌���̂��߂̊����ɌW��w���ւ̑Ή��Ȃ�
�E��L���͎w���Ŏg�p���镨�i�̍w���ɗv������K
�A�ȏ�ȊO�i���i�̔̔��X�Ȃǁj�Ɏx���������
�E���玑���ɏ[�Ă邽�߂̋��K�ł����āA�w�Z�����K�v�ƔF�߂�����
- ����҂̗]����Y��K�v�Ƃ��鐢��ɈϏ�����V�X�e���Ƃ��āA�ɂ߂č����I�Ȃ��̂ł��낤�B
�c����c�ꂪ�A���̏������v���C���������Ȃ�����̂ł�����B
�P�O�D�C�O�ςݗ��ē���
�E�q�ǂ����`�ŊC�O�ϗ�������������@������B
�N�P�P�O���~�̑��^�ł̔�ېŘg�𗘗p���āA�q�ǂ��̂��߂ɊC�O�ϗ����������Đߐł�����B
�E�ߐłƂƂ��ɁA�C�O�t�@���h�ʼn^�p���A�q���������̍��Y�𑝂₷���Ƃ��ł���B
�E����ɑΉ������l�X�ȋ��Z���i���o�ꂵ�Ă���B
�P�P�D�{�q���g �E�������Y�ɂ��ẮA�����l��l�ɂ��āA�T�O�O���~�̊�b�T��������B�����Q�V�N�P���P������̂��瑊���ɂ��ẮA�����l��l�ɂ��āA�R�O�O���~�ɂȂ�B
�]���āA�{�q��������Ƒ����̊�b�T���𑝂₷���Ƃ��ł���B
�E�������A��b�T�������₹��̂́A���q������ꍇ�͂P���܂ŁA���Ȃ����͂Q���܂łł���B
�P�Q�D��n�╧��ȂǂO�ɍw������
�E�������Y�����k�ł��邩��ł���B
�E��b�T�����邩�ǂ��������ȂƂ��ɂ́A���ʓI�ł���B
�P�R�D�C�O�ڏZ�͂ǂ���
�E���ɂ̐ߐŕ��@�́A�����ł��Ⴂ�C�O�ɈڏZ���邱�Ƃł���B
���{�͐��E�ōł������ŗ��̍������ł���A�ǂ�ȍ��ɈڏZ���Ă������ł͉�����͂��ł���B���Ƃ��A�V���K�|�[���A�I�[�X�g�����A�A�j���[�W�[�����h�Ȃǂ̍��ɂ́A�������������ł②�^�ł����݂��Ȃ��B
�E�������A���̂��߂ɂ́A�C�O�ł̖@�l�ݗ���A�����l���푊���l�����̍��ɋ��Z���Ă��邱�Ƃ������ƂȂ邱�Ƃ������A�����ɂ̓n�[�h���͍����ł��낤�B
�E�Ŗ����ǂ͎��Y�̊C�O�ړ]�ɔ����ېœ���ɑ���Ď��̐������������Ă���̂ŁA�����͕s�ł���B
�P�S�D���� �\ ��i�I���̂߂�
�E���Z���Y���P�`�Q�����炢�̐l�́A���ݕs���Y�Őߐł�������A���Z���Y�̐��O���^�̂ق����L���Ȃ��Ƃ������B
�E�ۗL���Y�z���P�O���ȏ�̕x�T�w�ł́A�@�l�𗍂߂����ݕs���Y�̊��p���A�ߐŌ��ʂ��傫���B
�E�s���Y�������P�O�O�O���~�ȏ�̐l�́A�s���Y��@�l�Ŋ��p����ƌ��ʓI�ł���B
�E�e��ߐō�́A�푊���l�̔N����l�����邱�ƁB��ʓI�ɂU�O���炢�̔�r�I�Ⴂ���͌��ʂ��傫�����A�N��オ��ƁA���ʂ������Ȃ邱�Ƃ������B
| ��Q�́@������\�����̐ߐł��낢�� |
 |

�����J�n��ɂ����ẮA�s���Y�]���̈��k���d�v�ł���B�|�C���g��������悤�B
�E�����ł̉����̃|�C���g
�P�D�L��n�̕]����
�E�L��n�́A���̏����̂��Ƃŕ]����������B
�E�L��n�Ƃ́A���̒n��ɂ�����W���I�ȑ�n�̒n�ςɔ䂵�Ē������n�ς��L��ȑ�n�ŁA�s�s�v��@��4���12���ɋK�肷��J���s�ׂ��s���Ƃ����ꍇ�Ɍ������v�I�{�ݗp�n�̕��S���K�v�ƔF�߂�����̂������B�������A��K�͍H��p�n�ɊY��������̋y�ђ����w�̏W���Z��̕~�n�p�n�ɓK���Ă�����̂͏������B
- �s�X�����
�O��s�s���@ �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E 500�u�ȏ�
����ȊO�̒n�� �E�E �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E 1,000�u�ȏ�
- ��������s�s�v����y�я��s�s�v���� �@�E�E�E�E�E�E�E�E 3,000�u�ȏ�
�E�L��n�̉��z�́A���Ɍf����敪�ɏ]���A���ꂼ�ꎟ�ɂ��v�Z�������z�ɂ���ĕ]������B
�@ �L��n���H�����n��ɏ��݂���ꍇ
�@ �L��n�̉��z���L��n�̖ʂ���H���̘H�����~�L��n����~�n��
�@ �L��n������O�D�U�|�O�D�O�T�~�L��n�̒n�ρ��P�C�O�O�O�u
�A �L��n���{���n��ɏ��݂���ꍇ
�@ ���̍L��n���W���I�ȊԌ������y�щ��s������L�����n�ł���Ƃ����ꍇ�̂P������̉��z���A
�@ ��L(1)�̎Z���ɂ�����u�L��n�̖ʂ���H���̘H�����v�ɒu�������Čv�Z����B
�Q�D���K�͑�n���̕]����
- ����̊T�v
�l���A�������͈②�ɂ��擾�������Y�̂����A���̑����̊J�n�̒��O�ɂ����Ĕ푊���l���̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă�����n�����͔푊���l���̋��Z�̗p�ɋ�����Ă�����n���̂����A���̑I�����������̂Ō��x�ʐς܂ł̕����i�ȉ��u���K�͑�n���v�Ƃ����j�ɂ��ẮA�����ł̉ېʼn��i�ɎZ�����ׂ����z�̌v�Z��A���̊��������z���܂��B���̓�������K�͑�n���ɂ��Ă̑����ł̉ېʼn��i�̌v�Z�̓���Ƃ����B
�@�Ȃ��A�����J�n�O3�N�ȓ��ɑ��^�ɂ��擾������n���⑊�������Z�ېłɌW�鑡�^�ɂ��擾������n���ɂ��ẮA���̓���̓K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ�
�i���j1.�푊���l���Ƃ́A�푊���l���͔푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă����푊���l�̐e���������B
2.��n���Ƃ́A�y�n���͓y�n�̏�ɑ����錠���ŁA���̌������͍\�z���̕~�n�̗p�ɋ�����Ă�����̂������B
�@�������A�I�����Y�y�т���ɏ����鎑�Y�ɊY�����Ȃ����̂Ɍ�����B
�����蓯����Њ����̕]�����Ƃ͑I��I�K�p�ƂȂ�B
- ���z����銄����
����22�N4��1���Ȍ�ɑ����̊J�n�̂������푊���l�ɌW�鑊���łɂ��āA���K�͑�n���ɂ��ẮA�����ł̉ېʼn��i�ɎZ�����ׂ����z�̌v�Z��A���̕\�Ɍf����敪���ƂɈ��̊��������z����B
�����J�n�̒��O�ɂ������n���̗��p�敪 |
�v�� |
���x�ʐ� |
���z����銄�� |
�푊���l���̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă�����n�� |
�ݕt���ƈȊO�̎��Ɨp�̑�n�� |
�@ |
���莖�Ɨp��n���ɊY�������n�� |
400�u |
80�� |
�ݕt���Ɨp�̑�n�� |
���̖@�l�ɑ݂��t�����A���̖@�l�̎���
(�ݕt���Ƃ�����)�p�̑�n�� |
�A |
���蓯����Ў��Ɨp��n���ɊY�������n�� |
400�u |
80�� |
�B |
�ݕt���Ɨp��n���ɊY�������n�� |
200�u |
50�� |
���̖@�l�ɑ݂��t�����
���̖@�l�̑ݕt���Ɨp�̑�n�� |
�C |
�ݕt���Ɨp��n���ɊY�������n�� |
200�u |
50�� |
�푊���l���̑ݕt���Ɨp�̑�n�� |
�D |
�ݕt���Ɨp��n���ɊY�������n�� |
200�u |
50�� |
�푊���l���̋��Z�̗p�ɋ�����Ă�����n�� |
�E |
���苏�Z�p��n���ɊY�������n�� |
240�u |
80�� |
1�@�u�ݕt���Ɓv�Ƃ́A�u�s���Y�ݕt�Ɓv�A�u���ԏ�Ɓv�A�u���]�Ԓ��ԏ�Ɓv�y�ю��ƂƏ̂���Ɏ���Ȃ��s���Y�̑ݕt�����̑�����ɗނ���s�ׂő����̑Ή��Čp���I�ɍs���u�����Ɓv�������i�ȉ����j�B
2�@�u���x�ʐρv�ɂ��ẮA�u���莖�Ɨp��n���v�A�u���蓯����Ў��Ɨp��n���v�A�u���苏�Z�p��n���v�y�сu�ݕt���Ɨp��n���v�̂��������ꂩ2�ȏ�ɂ��Ă��̓���̓K�p���悤�Ƃ���ꍇ�́A���̎Z�������ʐς����ꂼ��̑�n���̌��x�ʐςɂȂ�܂��B
A�{(B�~5/3)�{(C�~2)��400�u
�@A�F�u���莖�Ɨp��n���v�A�u���蓯����Ў��Ɨp��n���v�̖ʐς̍��v(�@�{�A)
�@B�F�u���苏�Z�p��n���v�̖ʐς̍��v(�E)
�@C�F�u�ݕt���Ɨp��n���v�̖ʐς̍��v(�B�{�C�{�D)
- ����̑ΏۂƂȂ��n��
���̓���́A���莖�Ɨp��n���A���苏�Z�p��n���A���蓯����Ў��Ɨp��n���y�ёݕt���Ɨp��n���̂����ꂩ�ɊY�������n���ł��邱�Ƃ��K�v�ł���B
�����莖�Ɨp��n����
�����J�n�̒��O�ɂ����Ĕ푊���l���̎��Ɓi�ݕt���Ƃ������B�ȉ������j�̗p�ɋ�����Ă�����n���ŁA���̕\�̋敪�ɉ����A���ꂼ��Ɍf����v���̑S�ĂɊY������푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾�������̂������i���̕\�̋敪�ɉ����A���ꂼ��Ɍf����v���̑S�ĂɊY�����镔���ŁA���ꂼ��̗v���ɊY������푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾���������̊����ɉ����镔���Ɍ�����j�B
�����莖�Ɨp��n���̗v��
�敪 |
����̓K�p�v�� |
�푊���l�̎��Ƃ̗p��
�����������n�� |
���Ə��p�v�� |
���̑�n���̏�ʼnc�܂�Ă����푊���l�̎��Ƃ𑊑��ł̐\�������܂łɈ����p���A���A���̐\�������܂ł��̎��Ƃ��c��ł��邱�ƁB |
�ۗL�p���v�� |
���̑�n���𑊑��ł̐\�������܂ŗL���Ă��邱�ƁB |
�푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă���
�푊���l�̐e���̎��Ƃ̗p��
�����������n�� |
���ƌp���v�� |
�����J�n�̒��O���瑊���ł̐\�������܂ŁA���̑�n���̏�Ŏ��Ƃ��c��ł��邱�ƁB |
�ۗL�p���v�� |
���̑�n���𑊑��ł̐\�������܂ŗL���Ă��邱�ƁB |
�����苏�Z�p��n����
�����J�n�̒��O�ɂ����Ĕ푊���l���̋��Z�̗p�ɋ�����Ă�����n���ŁA���̋敪�ɉ����A���ꂼ��Ɍf����v���ɊY������푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾�������̂�����(���\�̋敪�ɉ����A���ꂼ��Ɍf����v���ɊY�����镔���ŁA���ꂼ��̗v���ɊY������푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾���������̊����ɉ����镔���Ɍ����܂�)�B�Ȃ��A���̑�n����2�ȏ゠��ꍇ�ɂ́A��Ƃ��Ă��̋��Z�̗p�ɋ����Ă�����̑�n���Ɍ���B
�����苏�Z�p��n���̗v��
�敪 |
����̓K�p�v�� |
�擾�� |
�擾�ғ����Ƃ̗v�� |
�푊���l�̋��Z�̗p��
�����������n�� |
�푊���l�̔z��� |
�u�擾�҂��Ƃ̗v���v�͖����B |
�푊���l�Ɠ������Ă����e�� |
�����J�n�̎����瑊���ł̐\�������܂ŁA�����������̉Ɖ��ɋ��Z���A���A���̑�n���𑊑��ł̐\�������܂ŗL���Ă���l |
�푊���l�Ɠ������Ă��Ȃ��e�� |
�@�y�чA�ɊY������ꍇ�ŁA���A���̇B����D�܂ł̗v�������l
�@ �푊���l�ɔz��҂����Ȃ�����
�A �푊���l�ɑ����J�n�̒��O�ɂ����Ă��̔푊���l�̋��Z�̗p�ɋ�����Ă����Ɖ��ɋ��Z���Ă����e���ő����l�i�����̕������������ꍇ�ɂ́A���̕������Ȃ��������̂Ƃ����ꍇ�̑����l�j�����Ȃ����ƁB
�B �����J�n�O3�N�ȓ��ɓ��{�����ɂ��鎩�Ȗ��͎��Ȃ̔z��҂̏��L����Ɖ��i�����J�n�̒��O�ɂ����Ĕ푊���l�̋��Z�̗p�ɋ�����Ă����Ɖ��������j�ɋ��Z�������Ƃ��Ȃ����ƁB
�C ���̑�n���𑊑��ł̐\�������܂ŗL���Ă��邱�ƁB
�D �����J�n�̎��ɓ��{�����ɏZ����L���Ă��邱�ƁA���́A���{���Ђ�L���Ă��邱�ƁB
|
�푊���l�Ɛ��v����ɂ���
�푊���l�̐e���̋��Z�̗p��
�����������n�� |
�푊���l�̔z��� |
�u�擾�҂��Ƃ̗v���v�͂Ȃ��B |
�푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă����e�� |
�����J�n�̒��O���瑊���ł̐\�������܂ň����������̉Ɖ��ɋ��Z���A���A���̑�n���𑊑��ł̐\�������܂ŗL���Ă���l |
�����蓯����Ў��Ɨp��n����
�����J�n�̒��O���瑊���ł̐\�������܂ň��̖@�l�̎���(�ݕt���Ƃ������B�ȉ�����)�̗p�ɋ�����Ă�����n���ŁA���\�̗v���̑S�ĂɊY������푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾�������̂�����(���̖@�l�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă��镔���ŁA���\�Ɍf����v���̑S�ĂɊY������푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾���������̊����ɉ����镔���Ɍ�����)�B
�Ȃ��A���̖@�l�Ƃ́A�����J�n�̒��O�ɂ����Ĕ푊���l�y�є푊���l�̐e�������@�l�̔��s�ϊ����̑������͏o���̑��z��50������L���Ă���ꍇ�ɂ����邻�̖@�l(�����ł̐\�������ɂ����Đ��Z���̖@�l������)�������B
�����蓯����Ў��Ɨp��n��
�敪 |
����̓K�p�v�� |
���̖@�l�̎��Ƃ̗p��
�����������n�� |
�@�l�����v�� |
�����ł̐\�������ɂ����Ă��̖@�l�̖���(�@�l�Ŗ@��2���15���ɋK�肷�����(���Z�l������)������)�ł��邱�ƁB |
�ۗL�p���v�� |
���̑�n���𑊑��ł̐\�������܂ŗL���Ă��邱�ƁB |
���ݕt���Ɨp��n����
�����J�n�̒��O�ɂ����Ĕ푊���l���̑ݕt���Ƃ̗p�ɋ�����Ă�����n���ŁA���\�̋敪�ɉ����A���ꂼ��Ɍf����v���̑S�ĂɊY������푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾�������̂�����(���\�̋敪�ɉ����A���ꂼ��Ɍf����v���̑S�ĂɊY�����镔���ŁA���ꂼ��̗v���ɊY������푊���l�̐e�����������͈②�ɂ��擾���������̊����ɉ����镔���Ɍ�����)�B
���ݕt���Ɨp��n���̗v��
�敪 |
����̓K�p�v�� |
�푊���l�̑ݕt���Ƃ̗p��
�����������n�� |
���Ə��p�v�� |
���̑�n���ɌW��푊���l�̑ݕt���Ƃ𑊑��ł̐\�������܂łɈ����p���A���A���̐\�������܂ł��̑ݕt���Ƃ��s���Ă��邱�ƁB |
�ۗL�p���v�� |
���̑�n���𑊑��ł̐\�������܂ŗL���Ă��邱�ƁB |
�푊���l�Ɛ��v����ɂ��Ă���
�푊���l�̐e���̑ݕt���Ƃ̗p��
�����������n�� |
���ƌp���v�� |
�����J�n�̒��O���瑊���ł̐\�������܂ŁA���̑�n���ɌW��ݕt���Ƃ��s���Ă��邱�ƁB |
�ۗL�p���v�� |
���̑�n���𑊑��ł̐\�������܂ŗL���Ă��邱�ƁB |
 |
�R�D���דy�n�A�����̕]����
�E���דy�n�ɂ��ẮA��ʓI�ȕ]���z�����]���z�������邱�Ƃ��ł���B�����A�����邽�߂ɂ́A����A����𗧏���w�͂��K�v�ł���B
�E�ג����y�n�ȂǁA�s���Y�Ӓ�m�ɂ��Ӓ�]���ɂ��A�H���������Ⴍ�ł���B
�E�����Ɍ��ׂ�����ꍇ�́A�Œ莑�Y�]���z���A��z�ɂł���B
�S�D�ҕt�ɂ��ŋ���
�L��n�̕]�����A���K�͑�n���̕]�����A���דy�n�̕\�����Ȃǂ����p���Ȃ��������Ƃ���ɔ����������́A�T�N�ȓ��Ȃ�A�ҕt�\�i�����t���j�ł���B
|
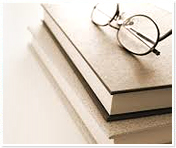



 ���������I�ł�������������̂�������Ȃ��B
���������I�ł�������������̂�������Ȃ��B
 �n�ɃA�p�[�g�����z���鎖��B
�n�ɃA�p�[�g�����z���鎖��B
